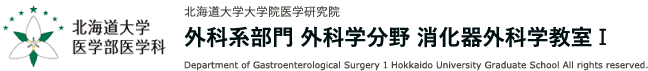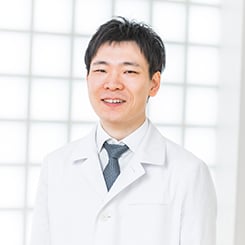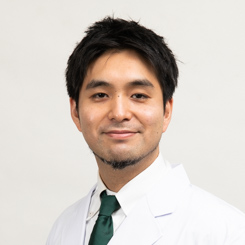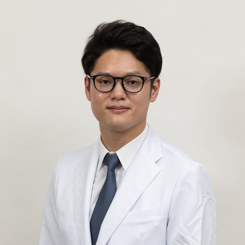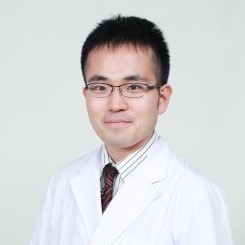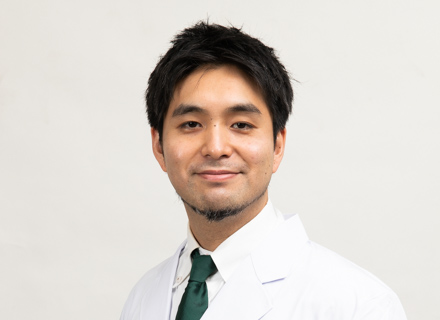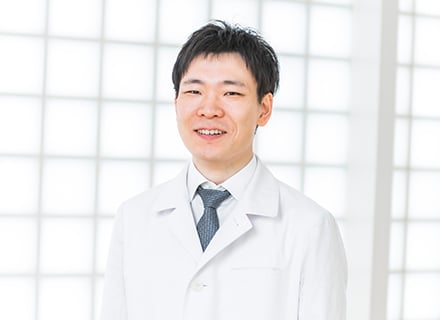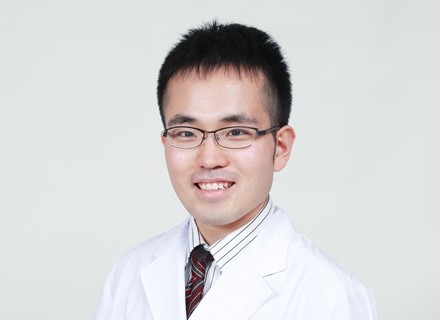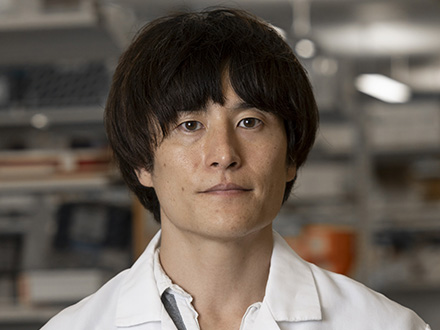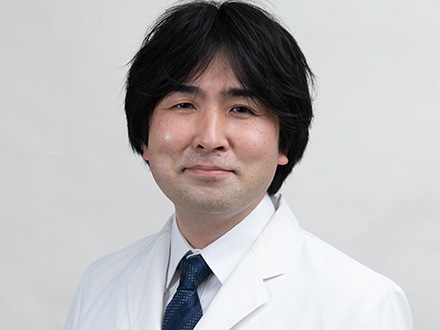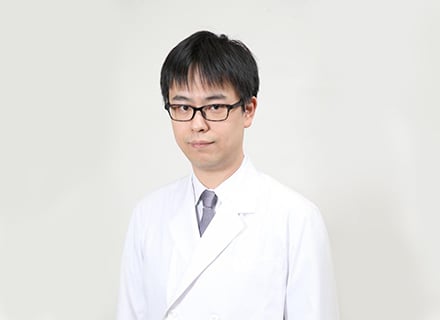
巖築 慶一
現在の留学先Massachusetts General Hospital
留学生活紹介
2009年卒の巖築です。現在、ボストンのMassachusetts GeneralHospital(MGH)でポスドクとして基礎研究に従事しております。MGHの業績は多方面にわたりますが、臓器移植の分野においても多くの業績を有しており、世界で初めて生体レシピエントへの豚腎の異種移植を成功させたことをご存知の方もいらっしゃると思います。その際に内科管理の責任者としてプロジェクトを支えたDr. Leonard V. Riellaの主催する研究室に私は所属しています。basicからclinicalまで幅広く研究しているラボで、そのうち私はBasicの部分の研究に携わっています。私には2つの研究テーマ、すなわちマウス心移植モデルを用いた新規免疫抑制剤の有効性とメカニズムの検証およびiPS細胞由来の腎オルガノイドを用いてバイオエンジニアリングの手法からミニ腎臓を作成する研究をさせて頂いています。新規免疫用製剤の研究では、薬剤の有効性、同薬剤が特定の種類の制御性T細胞を増加させることに加え、その免疫抑制作用がこれまで想定されていなかったものである可能性が示されており、今後さらに多くの発見が期待されます。まとまったデータが集まったので、とりあえず途中までの結果で論文を執筆中です。人工ミニ腎臓の研究は、工学系のラボとの共同研究で、共同研究者の作成したオルガノイド入り臓器カプセルをマウスに移植し、内部に血液を還流させる手術手技を用いて、作成したミニ臓器の有用性の検証を繰り返しています。詳細は割愛しますが、生体の腎臓に類似した構造および微小環境を人工的に再現できるかが成功への鍵だと思われるのですが、工学系の研究者にその重要性を理解してもらうのに日々苦労しています。この他にも、同僚の研究の手伝いでマウスの移植手術をするなど、外科医の比重が比較的高い仕事になっています。常に成果が求められ、比較的負荷の強い研究生活とはなっていますが、自分の仕事がイノベーションにつながっていることは強く実感でき、大きなやりがいを感じています。このような恵まれた環境で仕事ができるのも、人繰りの厳しい中送り出してくださった武冨先生ならびに教室のご配慮のおかげであり、この場を借りて感謝申し上げます。私生活に関しては単身赴任の形でこちらに赴任していることもあり、そこまでアメリカを楽めているわけではないとは感じています。一人暮らしの限界も日々感じ初めており、今後の家族のあり方を考慮すると、そろそろ帰国するタイミングとも考えております。
今後どのような選択をしたとしても、ここで学んだことや成果を何かしらの形で教室に還元できれば嬉しいと思いますので、何か相談ごとなどがありましたらどうぞご連絡いただければと存じます。今後ともよろしくお願い致します。
2023-24年の業績
論文
- Thiago J. Borges,Yoshikazu Ganchiku, Jeffrey O.Aceves, Ronald van Gaal, Sebastien G.M. Uzel, IvyA. Rosales, Jonathan E. Rubins, Kenichi Kobayashi, Ken Hiratsuka, Murat Tekguc, Guilherme T. Ribas,Karina Lima, Rodrigo B. Gassen, Ryuji Morizane, Jennifer A. Lewis, Leonardo V. Riella,Exploring immune response toward transplanted human kidney tissues assembled from organoid building blocks,iScience,2024,27 (10),110957,Original Article,10.1016/j.isci.2024.110957
- Orhan Efe,Rodrigo B Gassen, Leela Morena, Yoshikazu Ganchiku, Ayman Al Jurdi, Isadora T Lape, Pedro Ventura-Aguiar, Christian LeGuern, Joren C Madsen, Zachary Shriver,Gregory J Babcock, Thiago J Borges, Leonardo V Riella,A humanized IL-2 mutein expands Tregs and prolongs transplant survival in preclinical models.,J Clin Invest,2024,134 (5),e173107,Original Article,10.1172/JCI173107
学会
- American Transplant Congress,Philadelphia,2024/6/1-6/5,Yoshikazu Ganchiku,R.B.Gassen,O.Efe,Z. Shriver, G. J. Babcock, T. J. Borges, L. V.Riella,Tissue-Resident ST2+ Regulatory T Cells Promote Cardiac Transplant Tolerance Induced by aMutein IL-2,Oral Abstract session